10月「神無月」はどんな月か?神が出雲に集まる10月の行事、イベント、暦を知ろう!

10月神無月とはどんな月なのでしょうか。
秋の実りの季節。全国各地で1年の収穫を祝うお祭りや神事が行われます。穏やかな気候の中、様々なイベントも開催されます。
空気が澄み星の観察にちょうどいい季節ですね(^^^)
10月 神無月(かんなつき)

日本中の神様が出雲に集まる神無月は、神様にまつわるお祭りが全国で行われます。
出雲大社には、集まった神様が宿泊するところがキチンと用意されていました(ただし、小学生の時出雲大社で説明された話、「ここが泊まるところです」、、、と)
10月の行事

御九日(おくにち)

10月中旬ころ(旧暦9月9日)
旧暦9月9日重陽の節供の、その年の収穫を祝って行われる氏神の秋祭りです。
赤飯を炊き、甘酒を飲み、土地によっては茄子を食べる風習もあるとか。
長崎くんち(ながさきくんち)

10月7日〜9日
長崎諏訪神社の秋の祭りです(旧暦の月遅れの行事)。
神社本社での遷座式の後、町内の神輿を奉安し、氏子が笠鉾を先頭に龍踊りなどの奉納踊りを披露します。
体育の日(たいいくのひ)

10月第2月曜日
元々は、皆さんご存知の通り10月10日!
10月の第2月曜日となったのは、2000年(平成12年)から。ハッピーマンデー法及び移動祝日で定められたからで、なんだかピンとこないと思っているのはわたしだけ?
由来がある日の祝日を時の政権の都合で動かすのはどうなんだか?(月曜日を休みにして三連休にすれば国民がお金を使ってくれるのでは?という安易な政策と思う)
1964年(昭和39年)の東京オリンピックの開会式が行われた10月10日を、1966年(昭和41年)から国民の祝日となりました。
10月10日が開会式に選ばれた理由は、晴れの確率が非常に高いからと言われていますが、そうでもないらしい!
亥の子祭り(いのこまつり)

旧暦10月亥の日亥の刻(現在は11月に行うところが多い)
西日本各地の農村部で広く行われていた無病息災、子孫繁栄を祈る年中行事です。
亥の刻(21時から23時)に新穀でついた亥の子餅を食べ、子どもたちがワラ鉄砲や石を結んだ縄で地面を叩く「亥の子叩き」を行ったりします。
鹿の角切り(しかのつのきり)

10月上中旬の日曜祝日
牡鹿の角で被害を受けないよう、江戸時代から奈良春日大社で行われている行事です。
神の使いとされてきた鹿の角を切り落とし、神前に供えます。
神嘗祭(かんなめまつり)

10月15日〜
三重伊勢神宮でその年の初穂を天照大神に奉納し、翌年の豊作を祈願する儀式です。
べったら市(べったらいち)

新暦10月19日
東京宝田恵比寿神社で開かれている「べったら市」は江戸時代から続くものです。
よく20日に神社で行われる恵比寿講の前夜祭のようなもので「べったら漬け」を中心に数百軒の屋台が並びます。
恵比寿講(えびすこう)

旧暦10月20日
出雲に神が集まる神無月(旧暦10月)に留守をする恵比寿様の1年の無事を感謝します。
室町時代以降の商人の間で盛んになった商売繁盛祈願の行事。東日本では1月と10月の20日、西日本では、1月10日に行います。
時代祭り(じだいまつり)
 10月22日
10月22日
京都三大祭り。京都御所から平安神宮までの4.5キロを、平安遷都から明治維新までの華やかな装束を身にまとった人々が行列します。
霜降(そうこう)

10月23日ころ
この時期は気温が冷え込む早朝には霜が降り始めます!
紅葉や楓などが見ごろです。
ハロウィン

10月31日
ハロウィン、あるいはハロウィーンとは、毎年10月31日に行われる、古代ケルト人が起源と考えられている祭のこと。もともとは秋の収穫を祝い、悪霊などを追い出す宗教的な意味合いのある行事であったが、現代では特にアメリカ合衆国で民間行事として定着し、祝祭本来の宗教的な意味合いはほとんどなくなっている。
カボチャの中身をくりぬいて「ジャック・オー・ランタン」を作って飾ったり、子どもたちが魔女やお化けに仮装して近くの家々を訪れてお菓子をもらったりする風習などがある。
キリスト教の祭ではない。
ハロウィンに対してはキリスト教からは容認から批判まで様々な見解がある。
出典:ウイキペディア
わたしは子どもの頃全く存在を知りませんでした、何って聞かれてもさっぱり(笑い)!
神無月の名句
初しぐれ猿も子蓑をほしげ也(松尾芭蕉)
10月12日に亡くなった松尾芭蕉。芭蕉は時雨という季語を好んだことから、この日を時雨忌と言います。今年の初時雨で蓑を被ったが、猿もうれしそうに見えるという句!
紅葉や用意かしこき傘二本(与謝野蕪村)
紅葉が美しいころは時雨が降りやすい、
それを承知して傘を二本用意してきた賢い人がいる、という意味の句
なんで二本なんですかね、自分のなら1本でいいのでね(^^)
冷気が日ごとに加わり秋から冬へと移り変わる季節です。
10月(じゅうがつ)はグレゴリオ暦で年の第10の月に当たり、31日ある。
英語での月名、Octoberは、ラテン語表記に同じで、これはラテン語で「第8の」という意味の “octo” の語に由来している。一般的な暦では10番目の月であるが、紀元前46年まで使われていたローマ暦では、一般的な暦の3月が年始であり、3月から数えて8番目という意味である。
日本では、旧暦10月を神無月(かんなづき、かみなしづき)と呼び、新暦10月の別名としても用いる。
「かんな月」の語源
「かみな月」、「かんな月」の語源は不明である。以下のような説があるが、確かなものではない。いずれにしても「神無」は宛字としている。
醸成月(かみなしづき): 新穀で新酒を醸す月(大言海による)
神嘗月(かんなめづき): 新嘗(にいなめ)の準備をする月
神な月(かみなづき):「神の月」の意
雷無月(かみなしづき):雷のない月
出雲の出雲大社に全国の神様が集まって一年の事を話し合うため、出雲以外には神様が居なくなる月の意味というものがあり、これは平安時代から言われている民間語源(言語学的な根拠が無い、あてずっぽうの語源)である。出雲では神在月といわれる。
しかし、出雲へ行かず村や家に留まる田の神・家の神的性格を持つ留守神も存在し、すべての神が出雲に出向くわけではないとされる。異名
かみありづき(神在月)、かみさりづき(神去月)、かみなかりづき(雷無月)、かんなづき(神無月)、けんがいげつ(建亥月)、こはる(小春)、しぐれづき(時雨月)、じょうとう(上冬)、たいげつ(大月)、はつしもつき(初霜月)10月の季語
長月、秋の日、秋晴、秋高し、馬肥ゆる、秋の空、秋の雲、秋の山、秋の野、秋風、秋の声、 秋の暮、秋の雨、初紅葉、薄紅葉、桜紅葉、茸、初茸、湿地、椎茸、松茸、松茸飯、新米、新酒、 濁酒、稲、蝗、ばつた、稲雀、案山子、鳴子、鳥威、落し水、秋の川、渡り鳥、小鳥、鵯、百舌鳥、鶉、 懸巣、椋鳥、鶫、頬白、眼白、山雀、四十雀、鶺鴒、啄木鳥、木の実、桃、林檎、石榴、梨、柿、吊し柿、 無花果、葡萄、通草、椿の実、山梔子、杉の実、山椒の実、烏瓜、数珠玉、秋祭、菊、菊人形、野菊、 温め酒、牛祭、後の月、砧、やや寒、うそ寒、肌寒、朝寒、夜寒、べったら市、落花生、蕎麦、葦、荻、 火祭、木の実落つ、樫の実、栗、栗飯、団栗、胡桃、銀杏、棗、稲刈、稲架、樅、秋時雨、露霜、冬支度、 蜜柑、橙、朱欒、金柑、柚、秋深し、冬近し、紅葉、紅葉狩、柿紅葉、銀杏紅葉、蔦、蔦紅葉、草紅葉、鹿、猪、行秋、暮の秋、秋惜10月の年中行事
10月1日 – 衣替え(日本)
10月1日 – 建国記念日(中国)
10月3日 – ドイツ統一の日(ドイツ再統一記念日)(ドイツ)
10月10日 – 建国記念日(中華民国・台湾)
10月10日 (旧暦) – 十日夜(東日本)
10月13日-さつまいもの日
10月第1日曜日 – この日(年によっては3日)を最終日とするビール祭りオクトーバーフェスト(ドイツ)
10月第2月曜日 – 体育の日(日本)
10月第2月曜日 – 感謝祭(カナダ)
10月第2月曜日 – コロンブス記念日(アメリカ合衆国)
10月第2土曜日 – NARITA花火大会in印旛沼(日本・千葉県成田市)
10月第3日曜日 – 川越まつり(日本・埼玉県川越市)(日本三大山車祭りの一つ)
10月 (旧暦)の亥の日 – 亥の子(西日本)
10月31日 – ハロウィーン(キリスト教国を中心に世界中)
出典:ウイキペディア
1月から12月の行事ほこちらから調べられます!
2月「如月」はどんな月か?節分に冬の陰気を祓う2月の行事、イベント、暦を知ろう!
3月「弥生」はどんな月か?ひな祭りを祝う3月の行事、イベント、暦を知ろう!
4月「卯月」はどんな月か?桜を愛でる春4月の行事、イベント、暦を知ろう!
5月皐月はどんな月か?新緑まぶしい祭りの季節5月の行事、イベント、暦を知ろう!
6月「水無月」はどんな月か?雨の恵みに大感謝6月の行事、イベント、暦を知ろう!
7月「文月」はどんな月か?夏の夜空に願いを込めて7月の行事、イベント、暦を知ろう!
8月「葉月」はどんな月か?先祖の霊を供養する8月の行事、イベント、暦を知ろう!
9月「長月」はどんな月か?中秋の名月を楽しむ9月の行事、イベント、暦を知ろう!
10月「神無月」はどんな月か?神が出雲に集まる10月の行事、イベント、暦を知ろう!
11月霜月とはどんな月か?仕事に暦を活かすには行事を理解しよう!
12月の「師走」はどんな月か?12月の行事、イベント、暦を知ろう!
この記事は下記の本を参考にさせていただきました。
ありがとうございました。
旧暦で今をたのしむ「暮らし歳時記」
松村 賢治 (著)
旧暦を暮らしを取り入れて、季節の変化を楽しむための手引き書。季節ごとの行事や植物、食べ物、遊びなどを豊富なイラストで紹介する。
季節のうつろいを五感で味わい、心も体も豊かになる旧暦暮らしのすすめ!
桃の節句なのに桃が咲いていなかったり、七夕が梅雨の時期なのは、新暦に変わったから。もともとは行事食には旬の食材が使われ、あしらいにもその季節の植物が使われていました。旧暦を知ることで、日本の行事と四季が身近になります。
暦のある暮らし
松村賢治 (著)
暦の見方や暦を暮らしに生かす術を、昔の人に学び、生活に賢く取り入れる方法。旧暦時代から現代までつながる暦の見方がわかる。
旧暦から学ぶ季節の行事
年賀状、節分、虫干し、月見など、今や暮らしに溶け込み、なじみ深いものとなっている年中行事は数多くありますが、そのやり方をちゃんと知っている人は、ほとんどいません。本誌では、そんな季節ごとの行事のやり方を、先人から学ぶ教養として、イラストや写真を交えながら解説します。
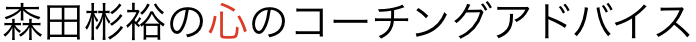




Facebookコメントはこちらにお願いいたします